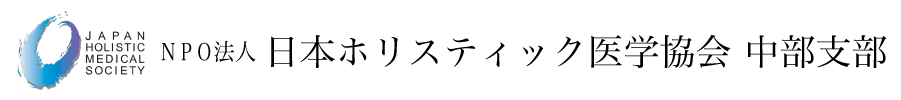■じつは「動物性たんぱく質」は摂りすぎてはいけない~現代ビジネス2024.7.9~
最近はちょっとしたたんぱく質ブームです。ただ、「たんぱく源として積極的に肉を食べましょう」という考えは、医師としてはあまりおすすめできません。地中海食は他の食事に比べて、タンパク摂取が少ないのも特徴です。タンパク質はアミノ酸からできていますが、アミノ酸摂取が減ると、乳がんや前立腺がんの予防効果に有効かもしれない、というデータもあります。女子栄養大学教授の上西一弘さん監修の『新しいタンパク質の教科書』。これによると、まず一般の人は「体重1kgあたり1g」が目安。つまり、体重60kgの人は1日60gということです。一方、高齢者は「一般人よりもちょっと多めの体重1kgあたり、1.2g程度が目安」とのこと。理由は、若い人よりも吸収能力が落ちているため、筋肉量を維持するには少し多めを意識してほしいからです。また、たんぱく質と一緒にビタミンB群やビタミンD、鉄、亜鉛も摂ると、たんぱく質の活性や合成がより高まるとも解説します。最後にもう一つ大事なことを。どんなにたんぱく質を摂っても、運動をしなければ筋肉はつきません。くれぐれも忘れないでください。
https://gendai.media/articles/-/133078
【バランスが大事、思考でなく・・・】
■新型コロナ、感染~完全回復までの期間?~ケアネットニュース2024.7.12~
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)感染後の回復期間の評価(米国・コロンビア大学I)。感染から回復までにかかった期間の中央値は20日、90日以内に回復しなかった人が推定22.5%いたことなどが判明した。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/58897
【長引く風邪!?】
■がんの70%を予防する10の方法が逆に意外!~現代ビジネス2024.7.1~
2007年、世界がん研究基金と米国がん研究機構は、それまでに世界各地でおこなわれた研究や大規模調査の結果を総合的に分析して、『食物、栄養、身体活動とがん予防:世界的展望)』という、ぶ厚い報告書を公表しました。そしてそのなかで、有効と思われるがん予防法を10項目示しています。
1 肥満をさける/2 よく体を動かす/3 カロリーの多い食品、糖分の多い飲料をさける/
4 植物性の食品を食べる/5 肉の摂取をひかえ、加工した肉は食べない/アルコールをひかえる/7 塩分をひかえ、カビのはえた食品は食べない/8 サプリメントに頼らない/9 できるだけ母乳で育てる/10 がんになったことがある人も、以上の助言に従う……ちょっと拍子抜けしませんでしたか?
https://gendai.media/articles/-/108270
【秘中の秘でなく・・・王道】
■5G電波のばく露レベル、4Gと同等かそれ以下~ITメディア2024.7.8~
情報通信研究機構は、商用運用されている5G携帯電話基地局からの電波ばく露レベルを測定した結果を発表。5G電波ばく露レベルの中央値は、人体に悪影響のない範囲を定める電波防護指針の約1万分の1以下に抑えられていた。データをダウンロードしていない時の電波ばく露レベルは、4G基地局の過去の測定結果を大きく下回った。ダウンロードしている時は、6GHz以下帯で約70倍、28GHz帯はで約1000倍になるが、その場合でも4G基地局と同等かそれ以下だった。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2407/08/news109.html
【安全と断言しているのでない、使いすぎに注意!】
■フラボノイド積極摂取で高血圧患者死亡リスク低減~ケアネットニュース2024.6.28~
米国疾病予防管理センター(CDC)の国民健康栄養調査のデータを用いた前向き試験によって、総フラボノイド摂取量が多いほど高血圧症患者の全死亡リスクが低減するという正の相関関係が認められた。フラボノイドは天然に存在するポリフェノール化合物で、主にフラバノン、フラボン、フラバノール、フラボノール、イソフラボン、アントシアニジンの6つ。多く含まれる代表的な食品として、柑橘類、野菜やハーブ類、緑茶やカカオ、ベリー類や葉物野菜、大豆製品、ブドウやベリー類があげられる。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/58786
【高血圧症疑いがある方、野菜・果物のすすめ】
■「10歳」若返る「すごい歩き方」
~現代ビジネス2023.12.30~
放っておくと筋肉は年齢と共に衰え、そのことが原因で免疫力が下がったり、生活習慣病を引き起こしたり、心の健康や、脳の認知機能にまで影響を及ぼすと言われています。そこでウォーキングの提案です。研究で、インターバル速歩を5ヵ月間実施すると、炎症促進遺伝子が不活性化され逆に炎症抑制遺伝子が活性化されることが明らかになった一方、同時にがんを引き起こす遺伝子が不活性化することも明らかになっている。やり方、足の踏み出しはできるだけ大股になるように行い、踵から着地する。この際、腕を直角に曲げ前後に大きく振ると大股になりやすい。速歩のスピードは個人が「ややきつい」と感じる運動である。すなわち、5分間歩いていると息が弾み、動悸がし、10分間歩いていると少し汗ばむ程度を目安とする。
https://gendai.media/articles/-/107488
【さぁ、今日から歩こう!】
■野生アフリカゾウ、互いに名前で呼んでいることが判明~ギガザイン2024.6.13~
ケニアのサバンナに生息するアフリカゾウの鳴き声を分析した新たな研究では、野生のゾウが「独自の名前」を持っており、この名前を使ってお互いを呼び合っていることがわかりました。研究チームは、ケニアのサンブル国立保護区とアンボセリ国立公園で1986~2022年にかけて録音されたアフリカゾウの鳴き声を機械学習モデルで分析。人間の可聴域を下回る低周波音「ランブル音」と呼ばれる「意図した受信者を識別できる名前のような要素」が含まれていました。
https://gigazine.net/news/20240613-elephants-call-each-other-by-name/
【パオ―~!!】
■お酒の種類と血圧の関係~ケアネットニュース2024.6.18~
アルコール摂取量は用量依存的に血圧の上昇と関連しており、その影響はアルコールの種類によらず同様であった(デンマーク・University of Southern Denmark)。アルコール摂取量が多いグループ(週 35 杯以上)と少ないグループ(週1~2杯)の間で、収縮期血圧は11mmHg、拡張期血圧は7mmHgの差が確認された。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/58768
【お酒は控えめに・・・】
■胃薬を飲むと胃がんに…そのクスリ~現代ビジネス2024.6.12~
胃薬を飲み続けると、胃がんになってしまうのか。主な原因は2つ。一つは、腸内細菌叢の変化です。本来は殺菌されて胃や腸にはいないはずの菌が胃に棲み着き、胃が荒れ、細胞ががん化すると考えられています。唾液などに含まれる口腔内常在菌は、ふつうは胃酸で殺菌されるので、胃や腸には棲み着くことができません。しかし、胃薬を飲んでいると殺菌効果が弱まり、胃や腸に口腔内の細菌が多く留まってしまう。なかでも歯周病菌は胃がんのリスクを高めると報告されています」。もう一つはホルモンに原因がある。胃酸不足に陥ると、胃酸分泌を促すガストリンというホルモンが多く出ます。PPIやP-CABを飲んでいる人の血液検査結果を見ると、飲んでいない人に比べて2~3倍もガストリン値が高い。実はこのホルモンに胃の腫瘍化を招くリスクがあり、胃がんにつながっているとみられています。「たとえばタケキャブは20mgと10mgの2種類がありますが、漫然と20mgを長期処方されているケースが多いので、医者と相談してみてもいいかもしれません」(新井氏)「PPIやP-CABよりは効果が弱い、H₂ブロッカーに切り替えてみるのもいいでしょう。いずれにせよ、毎日胃薬を飲まなければならない人は、内視鏡検査を定期的に受けることを強く勧めます。
https://gendai.media/articles/-/131067
【やたら薬に頼るのはダメ。。。】
■降圧薬の種類で認知症リスクが違う~日経メディカル2024.6.10~
高齢の高血圧患者に処方されている降圧薬の種類と認知症リスクについて検討し、アンジオテンシンIIタイプ2(AT2)受容体とタイプ4(AT4)受容体の刺激作用がある薬(ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬、サイアザイド系利尿薬)は、阻害する薬に比べ、認知症リスクが低かった(オランダAmsterdam大学)。
【自分の努力、生活習慣の見直しも・・・よろしく】
■飲酒で顔が赤くなる人は「コロナにかかりにくい」研究
~朝日デジタル2024.5.22~
お酒を飲むと顔が赤くなる人は、ならない人に比べて約5倍新型コロナウイルス感染症にかかりにくい――、佐賀大の研究グループ。顔が赤くなるアジアンフラッシュ体質の原因遺伝子を持つ人は、酒に含まれるエタノールの代謝物のアセトアルデヒドを解毒する酵素の働きが弱い。コップ1杯のビールで顔が真っ赤になるアジアンフラッシュ体質の人はアルデヒド類を解毒しにくいため、普段から体内のホルムアルデヒドの濃度が高めで、そのことがウイルスからの防御になっているのではないかという仮説を立てている。
https://www.asahi.com/articles/ASS5P4DNVS5PTTHB00GM.html
【酒は百+1薬の長!?】
■世界初〝食用〟ロボット、アンパンマンよりおいしさ感じるか
~産経新聞2024.5.23~
「こんにちは。今日、私はあなたと会話できることを楽しみにしてました」。音声とともに両手を振り、左右に揺れる全長約7センチの薄黄色の物体。つぶらな瞳もある。リンゴ味のグミだが、実はロボット(電気通信大)。ロボットはゼラチンでできた可食部と金属部分からなる。ゼラチンには空気穴が通り、ぷるぷると揺れる仕組みだ。音声はロボットに接続したスピーカーから出る。このロボットで一体何を行うのか。目指すのは「新たな食体験の創出」。そのヒントとして挙げたのが、国民的キャラクターのアンパンマンだ。「アンパンマンが顔をちぎり誰かに与えると、通常以上のおいしさを感じて元気が出る様子が描写されますよね」。食べ物との交流で、人の味覚に変化が起こるかもしれないと考え、研究を進めている。
https://www.sankei.com/article/20240523-D4ZOY7Y6AZKXBGITMIVU4WAHVI/
【元気100倍!みんなのアンパンマン】
■身体活動の指標、時間ではなく歩数でもOK?
~ケアネットニュース2024.5.31~
中~高強度身体活動に費やした時間と歩数を加速度計で連続7日間測定した。交絡因子調整後の中~高強度身体活動の時間および歩数と全死亡および心筋梗塞・脳卒中死亡の複合との関連を評価した。中~高強度身体活動時間の中央値は週62分、歩数の中央値は1日5,183歩であった。追跡期間中央値9.0年で、全死亡の1標準偏差当たりのハザード比は、中~高強度身体活動時間が0.82、歩数が0.74であった。中~高強度身体活動時間および歩数が多いほど生存期間が長かった。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/58623
【座りっぱなし生活からの脱却!】
■うつ病リスクと関連する飲料は?
~ケアネットニュース2024.6.3~
5年間のフォローアップを完了した8万497例のうち、1万8,172例がうつ病を発症した。高摂取群と非摂取群を比較した場合の完全調整後うつ病のリスク差は、次のとおりであった。【加糖飲料】3.6%【炭酸飲料】3.5%【野菜ジュース】2.3%【果汁100%フルーツジュース】2.4%【加糖コーヒー】2.6%【ブラックコーヒー】-1.7%緑茶は、統計学的に有意な差が認められなかった。著者らは「加糖飲料、炭酸飲料、野菜・フルーツジュース、加糖コーヒーはうつ病リスクを上昇させる可能性がある一方、ブラックコーヒーは低下させる可能性が示唆された」としている。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/58629
【甘い飲料はダメみたい。。。】
■国内最高齢の女性、糸岡富子さんが116歳に
~毎日新聞2024.5.23~
兵庫県芦屋市に住む国内最高齢の糸岡富子さんが116歳の誕生日を迎えた。暮らしている高齢者施設でお祝いのパーティーが開かれ、高島崚輔市長から花束が贈られた。糸岡さんは1908(明治41)年5月23日、大阪市で3人きょうだいの長女として生まれ、学生時代はバレーボールに親しんだ。90年に芦屋市へ移り住み、115歳だった2023年12月12日に国内最高齢となった。親族によると、趣味はお寺参りで、100歳を超えても浜手から山手の芦屋神社まで散歩していたという。車椅子を使用している現在も、背筋は真っすぐ。入所している市内の特別養護老人ホーム「Les(レ)芦屋」では、毎日リビングに出て好物の乳酸飲料を飲んだり、職員に「ありがとう」と声をかけたりして元気に過ごしているという。
https://mainichi.jp/articles/20240523/k00/00m/040/241000c
【お誕生日おめでとうございます!】
■風邪の予防・症状改善に亜鉛は有用か?
~ケアネットニュース2024.5.27~
8,526例が対象となったシステマティック・レビューの結果、予防目的での使用で、風邪症候群の発症リスクは、プラセボと比較してほとんどまたはまったく低下しない可能性がある(リスク比:0.93)。治療目的での使用では、風邪症候群の症状持続期間は、プラセボと比較して短縮する可能性がある(平均群間差:-2.37日)一方、非重篤な有害事象の発現リスクは、プラセボと比較して増加する可能性がある(リスク比:1.34)。「亜鉛は風邪症候群の予防には、ほとんどまたはまったく効果がないことが示唆される。一方、治療に用いる場合は、非重篤な有害事象を増加させる可能性はあるが、風邪の罹病期間を短縮する可能性がある」とまとめた。Maryland University of Integrative Health
https://www.carenet.com/news/general/carenet/58591
【新・風邪薬へ・・・・】
■がんの多くは「腸」に・・・ リスクを上げる食品、下げる食品
~東洋経済オンライン2023.5.29~
消化器外科医の石黒成治氏によると、がんのリスクを爆上げする食品①:超加工食品(スナック菓子、アイスクリーム、惣菜パン、シリアル、冷凍ピザ、ソーセージ、ハンバーガー、インスタント麺など)。爆上げする食品②:ブドウ糖果糖液糖。市販の清涼飲料水、フルーツジュース、ヨーグルト、乳酸菌飲料、めんつゆ、焼肉のたれ、ドレッシングなどのほとんどに入っており、工業的に作られた液状の糖です。果糖は果実に多く含まれている糖分で、砂糖の約1.5倍の甘さがあります。含まれる果糖が50%未満のものは「ブドウ糖果糖液糖」、50%以上90%未満のものは「果糖ブドウ糖液糖」と呼び名が変わります。爆上げする食品③:人工甘味料。対して、がんのリスクを最小化するもの①:食物繊維。最小化するもの②:植物栄養素。最小化するもの③:きのこ。最小化するもの④:発酵食品。
https://toyokeizai.net/articles/-/673721
【間違いなし!?】
■少し高い血圧でも脳・心血管疾患のリスクは2倍
~ケアネットニュース2024.5.20~
高血圧の治療中ではない就労者8万1,876人を9年間追跡調査。その結果、少し高い血圧の段階から脳・心血管疾患の発症リスクが高まることが確認された(J-ECOHスタディ)。正常高値血圧の段階から脳・心血管疾患発症リスクに対する取り組みが必要であることが明らかとなった。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/58520
【健康生活のすすめ】
■降圧薬を開始・追加した高齢者は〇〇に注意?
~ケアネットニュース2024.5.10~
高齢者は転倒リスクの1つである起立性低血圧が生じやすい。降圧薬が高齢者の骨折リスクへ及ぼす影響を検討した。その結果、降圧薬の開始・追加は骨折や転倒、失神のリスクを上昇させた(米国・Rutgers University)。100人年当たりの30日以内の骨折の発生率は、対照群が2.2であったのに対し、降圧薬開始・追加群は5.4であり、有意に骨折リスクが高かった(ハザード比:2.42)。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/58505
【それは・・・困る!?】
■世界初の「歯生え薬」9月に治験開始、京大発新興
~日経2024.5.3~
京都大学発スタートアップのトレジェムバイオファーマ(京都市)などは、歯を生やす抗体医薬品の臨床試験(治験)を9月に始めると発表した。歯を生やす薬の治験は世界初とみられる。生まれつき一部の歯が生えない「先天性無歯症」の患者向けに2030年の実用化を目指す。将来は虫歯などで歯を失った人にも応用したい考えだ。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF028KP0S4A500C2000000/
【もう一度、歯を再生!?】
■パラレルワールドとしての地球(山極壽一 地球研所長)
~YouTube動画~
現在、私たちは科学技術によってVRやメタバースなどの異世界を体験することができます。考古学や天文学の発達によって、映画や小説に過去や未来が登場し、それをバーチャルに体験できるようになって、時間も空間も超えるパラレルワールドを手中にできるようになりました。それが環境にどういう影響を与えるのか、歴史を遡って考えてみたいと思います。
https://youtu.be/aUDCZw9zm6c?si=80BS_m38fuCIdqM1
【ゴリラから人間を考える~助け合うこころ~】
■日本人の不眠症状と関連する要因
~ケアネットニュース2024.5.7~
不眠症は広くまん延しており、生活習慣病の発症や早期死亡のリスク因子となっている。不眠症状と関連する因子は、高齢、女性、現在の収入では生活が非常に困難な状況、痛み/不快感、不安、幸福感の欠如、頻繁な夜間頻尿、入浴から就寝までの長さ、寝室の照度、歩行時間の短さであった。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/58526
【解決方法は・・・?】
■コロナ禍以降、自宅での脳卒中・心血管死が急増
~ケアネットニュース2024.4.30~
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行期において、自宅や介護施設での脳卒中や心筋梗塞などの循環器疾患による死亡が増加し、2023年末時点でも循環器疾患による死亡のトレンドが減少していないことが明らかになった(白十字会白十字病院)。コロナ拡大後、病院外では死亡数が増加し続け、2022年の超過死亡率は、自宅では35%、介護施設/老人ホームでは23%に増加していた。一方、病院/診療所では、2020~21年に-5%まで一過性の減少を示したが、2022年には元のトレンドに戻った。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/58468
【続くコロナ禍。】
■祖先から数百万年感染し続けている2つのウイルス
~YouTube動画~
祖先から数百万年感染し続けている2つのウイルスとは口唇ヘルペスHSV-1と性器ヘルペスHSV-2。口唇ヘルペスHSV-1は世界人口37億人が感染(67%)、性器ヘルペスHSV-2は約5億人(13%)がすでに感染しているとみられる。
https://youtu.be/iRryFq0eXTw
【ウイルスには勝てない!?】
■大腸がんで死亡リスクが高くなる超加工食品は?
~ケアネットニュース2024.4.19~
大腸がんと診断された後の超加工食品摂取量と死亡率を調査した前向きコホート研究によって、アイスクリーム/シャーベットの摂取量が多いほど大腸がんによる死亡リスクが高く、超加工食品全体および油脂/調味料/ソースの摂取量が多いほど心血管疾患(CVD)による死亡リスクが高いことが明らかになった(中国・南京医科大学)。超加工食品の総摂取量が最も少ない五分位(中央値:3.6サービング/日)と比較して、最も多い五分位(中央値:10サービング/日)では、CVDによる死亡リスクが高かった(ハザード比:1.65)。超加工食品のサブグループ間では、アイスクリーム/シャーベットの摂取量が最も多い五分位では、大腸がんによる死亡リスクが高かった(ハザード比1.86)。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/58436
【和食、菜食中心がいいのかも・・・】
■国際消費品博覧会で医療機器の「ブラックテクノロジー」展示
~AFP通信2024.4.17~
直径約20~30マイクロメートルのガラスビーズ状の粒子の内部に放射性同位元素Y90を封入してカテーテルで患部に送り込む肝臓がん治療ツール「Y90ガラス微小球」、腫瘍疾患の検出に焦点を当てた人工知能画像設備、運動障害を持つ人の身体の鍛錬のため体重の一部を支える機能をもつ「反重力ランニングマシン」など、「第4回中国国際消費品博覧会」の「国際健康消費分会」のエリアでは、世界の最先端医療から「ブラックテクノロジー」満載の設備が数多く出展されている。ショールームには、不整脈治療用の「皮下植入型除細動器(S-ICD)」、心房細動治療用の「房室伝導パルスフィールドアブレーションシステム」、下肢静脈瘤治療用の「高周波閉塞システム」など、国際的な先端的な医療機器も多数展示されている。
https://www.afpbb.com/articles/-/3515334
【人造人間も間近か!?】
■脳の体積は「生まれた年代によって変化している」
~magmagニュース2024.4.11~
フラミンガム・ハート・スタディという大規模な虚血性心疾患の研究を元にしており、1930~1970年代に生まれた認知能力低下のない3,226人(平均57.7歳、53%が女性)が対象。1930年代生まれから、1970年代生まれまで、頭蓋内体積、脳の各所の体積を調べてみると、後の年代ほど体積が増大する傾向があった。例として、頭蓋内体積で示すと1930年代生まれに比べて1970代生では6.6%(1237mL)の増大があった。
https://www.mag2.com/p/news/596700
【1970-2020はどうなっている?】
■塩分摂取と認知症リスク
~ケアネットニュース2024.4.10~
食事による塩分摂取と認知症リスクとの因果関係を調査(中国・山西医科大学)。アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体型認知症など、さまざまなタイプの認知症リスクとの因果関係を推定した。欧州人を祖先に持つ人では、遺伝的に予測されたより高い塩分摂取量と全体的な認知症リスク増加についての関連性が示唆された(オッズ比:1.542)。明らかな不均一性や多面発現性は認められなかった。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/58375
【塩分を好んで過剰に摂りすぎるのは人間だけ!?】
■妊婦へのRSVワクチン、第3相試験が早期中止
~日経メディカル2024.4.8~
ベルギーGSK Belgium社のIlse Dieussaert氏らは、乳児の呼吸器合胞体ウイルス(RSV)感染症を予防する目的で、RSV融合前F蛋白質ベースのワクチン(RSVPreF3-Mat)の有効性と安全性を検討する第3相臨床試験を行い、妊婦1万人の登録を目標にしていたが、試験を早期中止した。ワクチン群の方が乳児のRSV感染症リスクは低かったが、プラセボ群に比べ早産リスクの増加が見られたため。早産は、プラセボ群乳児に比較して乳児ワクチン群乳児の相対リスクは1.37だった。新生児死亡の相対リスクは2.16。早産児の新生児死亡は、ワクチン接種群7人、プラセボ群0人に発生していた。RSV感染症は、生後2歳までにほぼ100%の幼児が罹患するが、生後6カ月未満で感染すると重症化しやすいため、ワクチンの開発が期待されていた。
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/nejm/202404/583818.html
【死亡するワクチン・・・なぜ!?】
■にんじんを生で食べるとビタミンCを破壊するって本当?
~ヨガジャーナル2024.3.24~
にんじんには「アスコルビナーゼ」という酵素が含まれています。この酵素はビタミンCを含むほかの食材と一緒に食べるとせっかくのビタミンCを破壊してしまうと言われてきました。しかし、近年の研究ではアスコルビナーゼは破壊しているのではなく、ビタミンCを「酸化」させているだけだそうです。酸化したビタミンCは、体内に入れば酸化前と同じビタミンCの働きをするため、ビタミンCは失われていないと考えられます。アスコルビナーゼは熱や酸に弱い性質をもっているので、もし不安な場合はこの性質を生かして、煮物や炒め物などすればアスコルビナーゼの働きを抑えられます。生でにんじんを食べる場合は、酸に弱い性質を生かして、酢や柑橘類で和えたマリネにしたり、酢の入ったドレッシングを使うことで、アスコルビナーゼの働きを防ぐことができます。にんじん入りの野菜ジュースを作るときは、レモン汁を加えるといった工夫をしてみましょう。
https://yogajournal.jp/22233
【お酢入りドレッシングでビタミンC・・・OK!】
■睡眠の質と「睡眠時無呼吸」が認知能力に影響する可能性
~magmagニュース2024.3.28~
一般地域の5つの集団からなる5,946人対象。循環器疾患や骨粗鬆症の状態等、他の状態像を揃え、眠りの状態による認知能力への影響を5年の経過で調べています。睡眠モニターで記録された睡眠中の覚醒時間は44~101分で、中度以上の睡眠時無呼吸は16.9~28.9%でした。睡眠が長時間維持できること、睡眠時無呼吸が少ないことが、認知能力の保持と関連していました。睡眠相の違いは、認知能力と関連を示していませんでした。長期にわたる睡眠の質の変化が、認知能力に影響を与えている可能性を感じる内容でした。
https://www.mag2.com/p/news/595554
【・・・どうすれば!?】
■老化を防ぎたいならコレに気をつけて
~Tarzan2024.4.2~
AGEは、糖質とタンパク質のアミノ基が結びついて生じる。基本的にタンパク質が豊富な肉類や魚介類に多い傾向がある。「高温で加熱するほど、食品中のAGEは増えます。とくに黒く焦げた部分にはAGEが多いので、避けるようにしてください。生で食べられる新鮮な魚介類はぜひ刺し身で。それ以外の魚介類や肉類は、茹でたり、蒸したりして調理しましょう。牛肉や豚肉は焼いたりせず、薄切り肉をしゃぶしゃぶで楽しんでください」揚げ物の油は170〜180度になるし、グリルの直火は300度を超える。一方、茹でる(しゃぶしゃぶを含む)、蒸すといった調理法はお湯や蒸気で加熱するから温度は100度以上にならず、AGEは必要以上に増えない。そしてAGE対策で絶対に欠かせないのが、禁煙。タバコは、生葉を高温乾燥させて作るから、その煙にはAGEがたっぷり含まれており、食べ物と同じく約7%が体内に入ってくるのだ。
https://tarzanweb.jp/post-303187
【和食中心で、加熱しすぎない。】
■高齢者の身体活動量、推奨値を変更/厚労省
~ケアネットニュース2024.3.19~
厚生労働省は身体活動・運動に関する推奨事項や参考情報をまとめた「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023」を2024年1月に公表。「健康づくりのための身体活動基準 2013」から10年ぶりの改訂。今回の改訂では、ライフステージごと(成人、こども、高齢者)に身体活動・運動に関する推奨事項をまとめるとともに、「慢性疾患(高血圧、2型糖尿病、脂質異常症、変形性膝関節症)を有する人の身体活動のポイント」「働く人が職場で活動的に過ごすためのポイント」など個人差を踏まえた推奨事項を示している点が大きな特徴。高齢者の推奨身体活動量を週10メッツから15メッツに変更、成人は1日約8,000歩以上、高齢者は約6,000歩以上を推奨など。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/58216
【万人の健康に貢献する運動を・・・】
■新型コロナによる世界の死亡率と平均余命への影響
~ケアネットニュース2024.3.22~
世界の成人死亡率は、2020年および2021年の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミック中に著しく上昇し、それまでの減少傾向が逆転した一方、小児死亡率は以前より緩やかではあるものの減少が続いていた(米国・保健指標評価研究所)。2020年と2021年を合計すると、世界中で推定1億3,100万人が死亡(全死因)し、そのうちCOVID-19パンデミックによるものは1,590万人であった。
https://www.carenet.com/news/journal/carenet/58274
【小児は新型コロナワクチン接種率が少ないという事実をどう考える!?】
■長生きの弊害、「健康寿命」が短縮
~ウォ~ルストリートジャーナル2024.3~
米ワシントン大学保健指標・保健評価研究所(IHME)の「世界の疾病負荷研究」による最新データの分析によると、人生のうち健康な状態で過ごせた割合の平均は2021年に83.6%となり、1990年の85.8%から低下したと推定されている。健康でいられる時間が減った一因は、医学の進歩により、かつては死に至った疾患が発見・治療されるようになったことにある。一方で、肥満・糖尿病・薬物使用障害といった疾患の有病率が上昇し、若年層でそうした傾向がよく見られることも影響している。健康状態が悪化すると、患者とその介護者に重い肉体的・精神的負担を強いる。また、家計を圧迫する医療費の高騰や、働きたくても働けない人の増加など、社会への影響も大きい。
https://jp.wsj.com/articles/your-healthspan-is-as-important-as-your-lifespanand-its-declining-099e90b6
【目指せ!死ぬまで現役】
■様々な癌で診断から数年間、骨折リスク増
~日経メディカル2024.3.6~
20種類の癌の病歴と骨折リスクについて検討するコホート研究を行い、癌の病歴がない対照群に比べ、様々な癌で骨折リスクの増加が観察された(英国London大学)。骨折のハザード比が最も大きかったのは、多発性骨髄腫で1.94、続いて前立腺癌の1.43だった。胃癌、肝癌、膵癌、肺癌、乳癌、腎癌、中枢神経系の癌のハザード比はいずれも1.20~1.50の範囲だった。また、悪性メラノーマ、非ホジキンリンパ腫、白血病、食道癌、大腸癌、子宮頸癌のハザード比は1.20未満だった。
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/lancet/202403/583385.html
【ガァ~ン!】
■ベンゾ1錠より呼吸法、不安時は「息を吐け!」
~2024.3.6日経メディカル~
不安を訴える患者に対して、抗うつ薬(SSRIまたはSNRI)の処方経験がなく、処方の仕方が分からないという医師はいまだに存在する。一方、不安に著効するベンゾジアゼピン系(BZ系)抗不安薬は常用量依存の問題があり処方しにくく、さらに、薬を服用したがらない患者もいるだろう。そんな時に実施したいのが、呼吸法の指導だ。不安症治療のための認知行動療法の一環である呼吸法は、シンプルなため外来でも勧めやすい(国立精神・神経医療研究センター)。(1)軽く息を吸い、(2)息を6秒ほどかけてゆっくり吐く、(3)3秒間息を止める──というサイクルの呼吸法を1回5~10分間、1日3回練習してもらいます。最初の練習は家の中で始めてもらい、家の中での練習に慣れたら電車の中や買い物中など、様々な場面で練習してもらいます。場所を切り替えることで、いつ不安に襲われても呼吸法で対処できるようになるためです。
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/202403/583414.html
【誰でも、どこでもOK】
■睡眠が認知症リスクに及ぼす影響
~ケアネットニュース2024.3.6~
日本人の中年期における睡眠時間およびその変化と認知症リスクとの関連を調査するため、本研究を実施した。その結果、長時間睡眠および睡眠時間の増加が認知症リスクと関連することが示唆された(長崎大学)。睡眠時間【10~12時間】ハザード比:1.40 睡眠時間の変化ハザード比【2時間以上の増加】1.37。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/58095
【睡眠の質にも問題があるかも・・・?】
■中国の中医薬資源は1.8万種余り
~AFP通信2024.3.2~
第4回全国中医薬資源調査により、中国には1万8817種類の中医薬資源があることが確認されたと発表されました(中国中医科学院中薬研究所)。この1万8000種余りの中医薬資源には、中国特有の薬用植物3151種、保護が必要な種464種が含まれています。また、今回の調査で新種が196種発見され、うち約100種が潜在的な薬用価値を持つということです。
https://www.afpbb.com/articles/-/3507048
【中国4千年の歴史の重さ】
■ブロッコリーが慢性炎症と死亡を低減
~ケアネットニュース2024.3.5~
ブロッコリーが、全身の慢性炎症と死亡率の低下に関連していたことが明らかになった(米国・サウスフロリダ大学)。ブロッコリーのカテゴリー(ブロッコリー、キャベツ、カリフラワー、芽キャベツ、ザワークラウト、キムチ)の摂取が最も一貫して炎症と死亡率の低下と関連していた。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/58122
【ブロッコリー、キャベツのサラダをどうぞ!】
■国内初の「飲酒ガイドライン」を公表/厚労省
~ケアネットニュース2024.2.22~
厚生労働省は飲酒に伴うリスクに関する知識の普及推進を図るために「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を公表した。本ガイドラインは、アルコール健康障害の発生を防止するため、国民一人ひとりがアルコールに関連する問題への関心と理解を深め、自らの予防に必要な注意を払って不適切な飲酒を減らすために、個人の適切な飲酒量・飲酒行動の判断の一助となるよう作成された。お酒に含まれる純アルコールに着目しながら、自身に合った飲酒量を決めて、健康に配慮した飲酒を心掛けることが必要。例:ビール500mL(5%)の場合の純アルコール量…500(mL)×0.05×0.8=20(g)純アルコール量で疾病発症リスク示す。脳卒中(脳梗塞)[男性:300g/週(40g/日)、女性:75g/週(11g/日)]・大腸がん[男性:150g/週(20g/日)、女性:150g/週(20g/日)]・乳がん[男性:データなし、女性:100g/週(14g/日)]など。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/58081
【お酒は嗜む程度に・・・】
■旅行先として最も魅力的な世界の都市
~アンケートによると2023.12.31~
ユーロモニター・インターナショナルの「旅行先として最も魅力的な世界の都市」によると ☆旅行先として最も魅力的な世界の都市
1.パリ、3年連続首位
2.ドバイ
3.マドリード
4.東京(前年20位)
http://questionnaire.blog16.fc2.com/page-1.html
【全ての食物が美味くて安い!】
■キノコと認知症リスク~日本での研究
~ケアネットニュース2024.2.13~
筑波大学の青木 鐘子氏らは、キノコ摂取と認知機能障害リスクとの関連を調査した。その結果、日本人女性において、キノコの食事摂取が認知機能障害リスクの低下と関連していることが示唆された。女性における認知症発症の多変量ハザード比は、キノコを摂取していなかった人と比較し、キノコの摂取量が0.1~14.9g/日で0.81、15.0g/日以上で0.56であった。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/58017
【おかずにキノコを食べることを忘れずに・・・】
■自転車通勤で糖尿病リスク関連慢性炎症が軽減
~ヘルスデーニュース2024.2.19~
自転車や徒歩で通勤している人は、2型糖尿病などのリスクと関連のある、全身の慢性炎症が軽減されていることを示すデータが報告された。ただし、有意な影響は、少なくとも45分以上の“アクティブな通勤”をしている人に限り観察されたという(東フィンランド大学)。
https://www.carenet.com/news/general/hdn/57956
【人間は歩くことが運動の基本】
■フレイル、「やせが多い」「タンパク質摂取が重要」は誤解?
~ケアネットニュース2024.2.8~
フレイルのリスク因子は、大きく分けて4つある。「代謝」、「糖尿病や高血圧症」、「がんの既往歴」、「肥満」。実際に、京丹後市のフレイルの人にはやせている人はほとんどいない。「睡眠」は、睡眠時間ではなく睡眠の質が重要。「運動」は、日常的な身体活動度の低さがリスク因子になっているという。「環境」は、これには食事、薬剤、居住地などが含まれる。厚生労働省が公開している「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、65歳以上の高齢者のフレイルやサルコペニアの発症予防には、少なくとも1g/kg/日以上のタンパク質摂取が望ましいとしている。しかし、これだけでは不十分である。高齢者の高タンパク質食は、サルコペニアの発症予防にならないどころか発症のリスクとなっているという報告もあり、単純にタンパク質を多く摂取すればよいわけではないことを強調した。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/57993
【総合としての健康管理が必要!】
■喫煙で男性型脱毛症リスク1.8倍、重症化も
~ケアネットニュース2024.2.12~
男性型脱毛症の発症および悪化の危険因子の関連の程度を調べたメタアナリシスの結果が発表された(カナダ・Mediprobe Research)。喫煙経験のある男性は喫煙経験のない男性に比べ、男性型脱毛症を発症する率が有意に高かった(オッズ比:1.82)。1日10本以上喫煙する男性は、1日10本未満の喫煙する男性に比べ、男性型脱毛症を発症する率が有意に高かった(オッズ比:1.96)。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/57972
【喫煙は百害あって一利なし。。。】
■中年期のタンパク質摂取が多いほど、健康寿命が延びる
~ケアネットニュース2024.2.2~
世界中で高齢化が進む中、健康寿命を延ばすことが求められており、栄養はその中の重要な要素である。中でもタンパク質は身体の健康維持に大きな役割を果たしているが、中年期にタンパク質を多く摂取した人ほど、疾病なく健康的に加齢する可能性があることが新たな研究でわかった(米国・タフツ大学)。中年期の食事からのタンパク質摂取、とくに植物性タンパク質摂取は、健康的な加齢の高いオッズ比および健康状態のいくつかの領域と関連しているようだ、と結論付けている。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/57924
【気にしながらタンパク質摂取を・・・】
■枕が高いと脳卒中に?
~ケアネットニュース2024.2.5~
脳卒中は高齢者で多いが、若年~中年者でも特殊な原因で起こることがある。その原因の1つである特発性椎骨動脈解離の発症と枕の高さの関連を、国立循環器病研究センターの江頭 柊平氏らが症例対照研究で検討したところ、枕が高いほど特発性椎骨動脈解離の発症割合が高く、また枕が硬いほど関連が顕著であることが示された。高い枕の使用に起因する特発性椎骨動脈解離患者は、12cm以上の枕で11.3%、15cm以上の枕で9.4%にみられた。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/57965
【そば殻のグスグス枕がいいかも!?】
■2050年の新規がん患者、3500万人に 22年比77%増 WHO
~AFP通信2024.2.2~
世界保健機関(WHO)の国際がん研究機関は、2050年に新たにがんと診断される患者数は、22年に比べて77%増え、3500万人を超えると警告した。
「世界で急速に増加しているがんによる負担は、人口の高齢化と増加に加え、危険因子への暴露の変化を反映しており、その一部は社会経済的発展に関連している」と指摘。喫煙、飲酒、肥満、大気汚染が増加の主因だとしている。
https://www.afpbb.com/articles/-/3503456
■疲労と日中の過度な眠気、どちらがよりうつ病と関連?!
~ケアネットニュース2024.1.30~
韓国の15の地区で本調査を実施した。【疲労あり、日中の過度な眠気あり】8.804/【疲労あり、日中の過度な眠気なし】3.942/【疲労なし、日中の過度な眠気あり】2.812。著者らは「疲労と日中の過度な眠気は、どちらがよりうつ病と密接に関連しているかは不明であったものの、それぞれが独立してうつ病と関連していることが示唆された」としている。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/57929
【慢性疲労と過度な眠気に気をつけましょう】
■韓国、出生率0.72人・・・「このままでは国が滅びる」
人口消滅の危機に直面している中、子どもを産みたくても産みにくい不妊夫婦も増えている。統計庁によると、不妊夫婦は2018年の11万6000人から2022年には14万3000人に急増した。そのため、不妊に備えるために卵子を凍らせ、子宮の健康を事前に確認しようとする人も少なくない。
https://www.afpbb.com/articles/-/3502357
【大問題!】
■朝食摂取とうつ病との関係
~ケアネットニュース2024.1.18~
朝食の摂取、食事性炎症指数とうつ病との関連を調査した(中国・吉林大学)。「朝食を抜くと食事性炎症指数Iが上昇し、うつ病リスクが高まる可能性がある(オッズ比:1.54)」と評価した。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/57845
【朝ごはん、食べよう!&炎症おこしにくい食事の摂取】
■黒砂糖、がん発症を抑制か
~ケアネットニュース2024.1.17~
長寿者の割合が比較的高く黒砂糖をおやつにしている奄美群島の住民を対象としたコホート研究を実施したところ、黒砂糖摂取ががん全体、胃がん、乳がんの発症リスク低下と関連することが示された(鹿児島大学)。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/57838
【奄美以外でも同じか?】
■尿が黄色くなるメカニズムが明らかに
~ケアネットニュース2024.1.12~
腸内細菌叢由来のビリルビン還元酵素(BilR)を同定し、この分子がビリルビンをウロビリノーゲンに還元し、ウロビリノーゲンが自然に分解されることで尿中の黄色色素ウロビリンが産生されることを明らかにした(米国・メリーランド大学)。
https://www.carenet.com/news/general/carenet/57833
【125年以上の謎がようやく解明】
■50歳男性、干し柿を一度に10個食べ十二指腸に穴の危険
~AFP通信2024.1.11~
中国の浙江省杭州市で、50歳男性の張さんが干し柿を一度に10個も食べた結果、危うく腸壁に穴が開いて命にかかわる状態になるということがありました。すぐに処置する必要があると判断。すぐに胃腸減圧を行うとともに胃カメラ検査を手配しました。検査の結果、張さんの胃にできた石が十二指腸下行部に落ち、十二指腸の閉塞をもたらしたことが分かりました。嵌頓(かんとん)が続けば、穿孔の恐れがあります。しかし結石嵌頓の位置が悪く、コーラや炭酸水素ナトリウムを飲んで溶解させる治療法を採用できなかったため、医療チームはすぐに内視鏡下砕石取石の手術を手配しました。張さんは治療を受けて回復し、すでに退院しました。「もう二度と干し柿をこんなにたくさん食べたりはしない」と話しました。
https://www.afpbb.com/articles/-/3499801
【何事もほどほどに・・・】
■「食塩の食べ過ぎ」による死亡率 中国が世界一
~AFP通信2024.1.5~
北京大学公共衛生学院栄養・衛生学部主任の馬冠生教授はこのほど、「現在、国民の食塩摂取量は1日当たり9.3グラムで、推奨されている5グラムを大幅に上回っていることが研究で分かった。中国人の食塩の食べ過ぎによる死亡率は世界一で、これは中国人の健康を害する重要な要素となっている」と発表しました。
https://www.afpbb.com/articles/-/3499051
【日本の昭和時代と同じぐらいか!?】
■長すぎてもダメ?睡眠時間による風邪のひきやすさ
~magmagニュース2024.1.5~
アメリカにおける研究で、全国規模の健康調査(2000,2015年)の結果を元としています。昼間の勤務で、7~8時間眠る人を標準として、短時間睡眠(5時間以下)、長時間睡眠(9時間以上)、シフト勤務の人で、過去2週間での感冒(風邪)への罹患状況を調べています。結果として、以下の内容が示されました。短時間睡眠の人は44%多く風邪にかかっていました。長時間睡眠の人は20%、シフト勤務の人も20%多く風邪にかかっていました。要約:『短時間・長時間の睡眠、シフト勤務で風邪に罹りやすくなる可能性がある』
https://www.mag2.com/p/news/590313
【標語「快眠快食快便」】
■働きアリ:2割程度は「働かず」
~毎日新聞2012/12/29~働きアリの集団の中には常に2割程度の働かないアリがいて、働くアリだけのグループを作っても必ず働かないアリが出ることを、長谷川英祐・北海道大大学院准教授(進化生物学)らが証明した。「働かないアリがいれば、別の仕事が生じた時にすぐに対応できる。仕事の効率は下がるが集団を維持する巧妙な仕組みではないか」と推測している。卵の世話をするなどの仕事量にばらつきがあり、どのコロニーにもほとんど働かないアリが約2割いた。働かないアリだけ30匹集めると、うち約2割が働かないままだが、残りはよく働くようになった。よく働くアリだけを集めて新たなグループを作っても一部は働かなくなった。仕事の熱心さに年齢などは関係なかった。人間社会のように集団に指示するボスはいないが、自然と働くものと働かないものが出る。長谷川准教授は「働かない『働きアリ』が集団維持にどのように貢献しているか今後明らかにしたい」と話している。
【働きすぎに注意しましょう!】
■2010年の世界的な平均余命、男性67.5年、女性73.3年
~ケアネットニュース2012.12.28~世界的な出生時平均余命の延長は1990年台にいったん停滞したが、1970~2010年の40年間で持続的かつ実質的に延長し、2010年には男性が67.5年、女性は73.3年に達したことが、米国・ワシントン大学のHaidong Wang氏らの調査で明らかとなった。
http://www.carenet.com/news/journal/carenet/32879
【伸びました。女性はやっぱり男性より5歳以上長生きなんだ。】
■ビールの苦味成分に感染症予防効果、ただし大量摂取が必要
~AFP通信2012年12月07日~サッポロビールは札幌医科大学との共同研究で、ビールの主原料ホップに含まれる苦味成分「フムロン」に急性呼吸器感染症を引き起こすRSウイルスの増加を抑制する働きがあることを発見したと発表した。感染後の炎症の緩和効果もあるという。RSウイルスに感染すると肺炎や気管支炎を発症する。大人では風邪のような症状となるが、乳幼児の場合は重症化することもある。ただし、感染予防に必要な量の「フムロン」をビールから摂取するには、350ミリリットル入りの缶ビールを30本飲まなければならない。このため「フムロン」を食品やノンアルコール飲料から摂取でき、特に苦味成分である「フムロン」を子どもにも食べやすい味にすることが大きな課題だという。
http://www.afpbb.com/article/life-culture/health/2915467/9957094
【缶ビール30本は、かなりの酒豪でないと無理→でも肝臓が・・・】
■フランス人男性の精子数、約15年で3分の1減 仏研究
~AFP通信2012年12月06日~フランス人男性の精子の数が1989年から2005年の間に3分の1減ったとする研究結果が欧州の学会誌「ヒューマン・リプロダクション」に発表された。「公衆衛生における深刻な警告だ。とりわけ環境との関連が究明される必要がある」と述べている。精液1ミリリットル当たりに含まれる精子数を示す精子濃度は年平均で約2%ずつ継続的に減少し全期間通しては32.2%減少していた。平均年齢35歳男性では、精子濃度は1989年には7360万個だったのが、2005年には4990万個に減っていた。一般的に精子濃度が5500万個を下回ると受胎率に影響が出るといわれ、1500万個を下回ると不妊の原因とみなされる。
http://www.afpbb.com/article/life-culture/health/2915364/9951314
【男たちよ!ガンバレ!】
■ハイリスクハイリターン好む=脳の領域突き止める-東北大
~時事通信2012/11/13~脳組織の一部「島皮質」が働くと、積極的にリスクを冒し、より大きな報酬を得ようと行動することを、東北大学大学院生命科学研究科の飯島敏夫教授らの研究グループがラットの実験で突き止めた。脳の前頭眼窩野がリスク行動を抑制することはこれまでにも知られている。研究グループは前頭眼窩野に隣接する島皮質前部には、反対にリスクを冒し、より大きな利益獲得を目指す行動を促進する機能があることを世界で初めて発見したという。
【ギャンブル依存症の治療法開発なるか!?】
■「褒められると伸びる」は本当~生理学研、実験で証明
~日本経済新聞2012/11/8~運動トレーニングをした際に他人から褒められると、上手に運動技能を取得できると、自然科学研究機構生理学研究所の定藤規弘教授らの研究グループが実験で明らかにした。グループの田中悟志名古屋工業大准教授(神経工学)は「褒めて伸ばすという言葉が科学的に証明された。教育やリハビリテーションの現場で応用できる」としている。研究では(1)自分が褒められる(2)他人が褒められるのを見る(3)自分の成績をグラフだけで見る――の3グループに分けた。翌日、運動直後に自分が褒められたグループは前日の練習から成績が20%伸びた一方、ほかの2グループは13~14%の伸びにとどまった。これまでの研究で、うれしいことがあると、脳内で記憶の定着に重要な役割を果たすドーパミンが分泌されると判明しており、田中准教授は「褒められた分、記憶が残って動きが良くなったのではないか」と話している。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0800O_Y2A101C1CR0000/
【子どもだけでなく、大人になっても褒めてあげよう!】
■肥満と誤診の女性から28キロの腫瘍摘出
~AFP通信2012年10月29日~ドイツ東部ドレスデンの大学病院は、60歳のイルムトラウト・アイクラーさん(女性)から重さ28キログラムもの腫瘍の摘出に成功したと発表した。彼女は別の病院で過度の肥満と診断され、原因は糖尿病と運動不足だとして抗肥満薬を処方されていた。しかし、むくみがひどく立ち上がることもできなくなったため、セカンドオピニオンを求め、大学病院での超音波検査で、縦60センチメートル、横50センチメートルにもなる大きな「境界悪性腫瘍」(良性ではないが悪性度の低い腫瘍)が卵巣に癒着しているのが見つかった。子宮、卵巣、甲状腺も肥大して気管を圧迫し、アイクラーさんは呼吸も苦しい状態だったという。手術では腫瘍のほか、これらの肥大していた臓器も摘出された。その結果、危険なレベルまで増えていた体重は40キロ減少したという。
http://www.afpbb.com/article/life-culture/health/2909690/9754106
【40キロ減量!よかったねと言うべきか、否か!?】
■山中教授の「下手な」イラスト、研究進める決め手に
~2012年10月9日読売新聞~山中教授がノーベル賞授賞理由となったiPS細胞(新型万能細胞)の研究を飛躍させた原動力は、自分で作成した個性的なイラスト。イラストの図柄は、人の胚(受精卵が成長したもの)や腫瘍のできたマウスが涙を流す様子を描いていた。審査担当だった岸本忠三・元大阪大学長は「イラストを使った説明には(説得する)迫力があった。(iPS細胞は)できるわけがないとは思ったが、『百に一つも当たればいい。こういう人から何か出てくるかもしれん。よし、応援したれ』という気になった」と評価した。これで約3億円(5年分)という巨額の研究費を獲得した。
【下手でも十分な説得力があった。中身が大事なのよね~何事も】
■子どもの野菜嫌い、楽しい「ネーミング」が効果 米研究
~AFP通信 09月26日~「子どもに野菜をもっと食べさせたい」ブロッコリーを「小さなおいしい木のてっぺん」と名づけるなど、野菜を楽しい名前で呼ぶことで子どもたちが残さず食べるようになったという。この論文は学術誌「予防医学(Preventative Medicine)」に掲載された。米コーネル大学が行った実験「ヘルシーな食材に魅力的な名前をつけることで、子どもたちがその食材を選び、食べるようになる(最高99%まで上昇した)。「着実に効果があり、しかも大規模に展開できる上にコストがほとんど、あるいは全くかからない」と研究チームはまとめている。
http://www.afpbb.com/article/life-culture/health/2902616/9556095
【野菜好きな子どもが増え、争いのない平和な社会になるといいね!】
■タニタが教えるダイエットルール
~MSNニュース~やせるつもりがかえって太る?自己流ダイエットの落とし穴。食べない、あるいは食事の量を減らすと、脂肪より先に筋肉量が低下し、ホルモンバランスが乱れる。これにより、ダイエットを始める前よりも太りやすい体質になってしまう。ダイエットのために1日の摂取カロリーを1000kcal以下に抑えると、からだは少ないカロリーでも活動できるようにと基礎代謝を低下させ、一種の省エネ状態になる。こうなってしまうと、食事の量を減らしても体重が落ちなくなるうえ、飢餓に備えて脂肪をためやすい状態になり、ちょっと多く食べただけですぐに太ってしまうのだ。タニタが勧めるダイエットルールは次のよう。
・主食を減らして、たんぱく質をプラスし食欲を抑制する・大豆製品や豆類、酢などをプラスして、肥満ホルモンの分泌を抑える・ご飯は最後に食べる など。
【勘違いの多いダイエットルール。さすがタニタさん!】
■ほうれい線、1センチ伸びれば6歳老ける
~ロート製薬2012年9月4日~肌のハリが失われてくると目立つ「ほうれい線」。ほうれい線が特に女性の見た目年齢に影響を与えていることが明らかになった。この調査では、画像加工でほうれい線の長さのみを変えた2種類の女性の顔写真を用意。2枚の写真を比較して「何歳差に見えるか」を尋ねた。すると、ほうれい線を1.18センチ伸ばしただけの写真の方が平均6.93歳も老けて見られた。1センチあたりに換算すれば、6歳老けるという計算になる。
【印象の鍵は肌のハリ。恋多き女性ほど肌にハリがあることもわかった】
■都市伝説(ではなかった!!)「○○すると死ぬ」説
~MSNトピックス8/16~子ども時代の夏、親に「扇風機をつけっぱなしにして寝ると死ぬよ」と言われませんでしたか?「○○すると死ぬ」という都市伝説はいくつかありますが・・・。●扇風機にあたり続ける―近距離で強い風にあたり続けると体温が下がり血管が収縮することによって心筋梗塞や脳梗塞が誘発されるといいます。● ぎんなんを食べすぎる―「4′-メトキシピリドキシン」という成分がビタミンB6のはたらきを阻害して欠乏させ、嘔吐やけいれんなどの中毒を起こすことがある。成人の場合は40粒以上食べると中毒の危険性があるそうです。
【侮れない!都市伝説】
■ストレス多い男性は太目の女性を好む? 学術研究で判明
~CNN 2012.08.10~精神的ストレスを感じている男性は、太った女性に魅力を感じる傾向がある――。そんな調査結果が米科学誌プロスワンの今週号に発表された。社会の理想とする体型が資源利用に左右されることは、学会では定説だった。食糧不安などに脅かされている状況では、困難な環境で生き延びる能力が高いとみなされ太目の女性が好まれる。現代社会では失業などの問題でもこうした不安に該当し得るほか、過去の研究では、男性が空腹になると太目の女性を魅力的と感じる傾向があることも分かっている。
http://www.cnn.co.jp/fringe/35020335.html
【ぽっちゃり系女子は男性のストレス解消と安心に・・・科学的!?】
■ロシアで『不老不死』の研究キターーッ!2045年には「死」がなくなる
~ライブドアニュース2012年08月08日~ロシアの研究家ドミトリー・イスコフ氏(31)は不老不死の研究で、2045年までに人類から「死」という概念が一切消えるという。不老不死の状態を得る方法は突拍子も無いもので、SFの世界の話のようなものだ。平たく言えば人間の『脳』をバックアップ、そして機械に転送するという。2025年にロボットに人間の脳を転送可能に、2035年にはアバターによる脳が作成人格が注入、 2045年にはついに人類から「死」がなくなるという。
【死にたくても死ねない!という苦痛が待っているかも!?】
■カレーは・・・脳によい=茂木健一郎氏発表
脳科学者の茂木健一郎氏が壇上で強調した。「ね、びっくりする結果じゃないでしょ。脳科学では、みんなが直感的に思っていたことが、あらためて実証されることが多いんですよ」――。第11回カレー再発見フォーラムでの発言。カレーの香りを嗅ぎ、食べることで、被験者のストレスが抑えられ、作業に対するモチベーションが維持された。疲労も軽減されたという結果が出た。茂木の説明に、出席した一同もうなずいた。
【どこのカレーが一番かも知りたい。できれば辛さも。】
■NASAの宇宙ドリンクに若返り効果、肌の自己修復力アップ
~6月3日 AFPBB News~NASAが開発した「宇宙ドリンク」に肌の若返り効果があるという。果たしてSFのような夢物語なのか、それとも本当に若返りの泉なのか。このドリンク(AS10)は、宇宙飛行士を放射線から守るために開発したものだが、老化した肌を若返らせる効果があるらしい。ユタ大学の研究チームは、被験者180人にAS10を4か月にわたり1日2杯ずつ飲んでもらった。結果、紫外線による顔のしみは30%、しわについても17%の減少がみられた。AS10にはクプアスやアサイ、アセロラ、ウチワサボテンの実、ヤマモモといったフルーツに加え、緑茶やザクロジュースが含まれており、抗酸化作用が高いという。ただし、740ミリリットル入りボトル1本当たり約3900円と少々値が張るのが難点。1日に約60ミリリットルを服用した今回の実験では、4か月間で約3万6000円がかかった。
http://www.afpbb.com/article/life-culture/health/2881463/9034506
【銀河系「宇宙ドリンク」。日本上陸の日も近い!】
■「注射されているところを見ると痛みが増す」という研究発表
~2012.05.30 ギズモード・ジャパン~注射をされているビデオ、綿棒でつつかれているビデオ、何も起きないビデオの3種類のビデオを見せました。注射をされているビデオを見た人は、痛みをより強く感じました。それだけではなく、「綿棒の方が注射よりも痛い」ということを言われて実験に臨んだ人は、綿棒のビデオで一番痛みを感じました。つまり痛みを与えると思っているものを見ることは、痛みをより強く感じさせるように働くということです。研究したのはベルリンにある聖ヘドウィグ病院のチーム。ということで、注射されている所を凝視するのは、痛みを増すだけなので止めた方がよさそうです。逆に痛いのがお好きな方は試してみてもいいかもしれませんね。。。
http://www.gizmodo.jp/2012/05/post_10421.html
【注射・・・嫌い!!!】
■かき氷頭痛「キーン」の原因、わかりました。
誰もが経験したことがあろう、あのキーン! あのキーンの正体が解明されたそうです。研究は、ハーバード大学医学校でなされました。冷たいものを摂取すると、前大脳動脈の拡張が起こり、結果として痛みが生じるということでした。脳は人間の身体の中でも常に動いている必要がある、重要な器官の1つです。また温度に敏感な器官でもあります。血管拡張は脳の温度が下がらないように温かい血液を送ることによって起きるのではないでしょうか。
http://www.gizmodo.jp/2012/05/gw_21.html
【キーンがあっても食べたくなるかき氷の季節が今年もやってくる。】
■悪夢から解放、楽しい夢にするアプリ
心理学の権威として知られる、ハートフォードシャー大学のリチャード・ワイズマン博士は、アプリ開発メーカー『YUZU』と協力して、悪夢を解消するアプリを開発した。使い方は「起床時間」と「アラーム音」、そして「サウンドスケープ」と呼ばれる音を設定するだけ。サウンドスケープとは、ユーザーが夢を見始めた段階で鳴る環境音楽であり、この音を眠りながら聞くことによって、悪夢を解消するとのこと。データ的に21パーセントが不快な夢を見て、15パーセントが悪夢に苦しめられている。このアプリ使用で、ロンドンでは32パーセントの人が楽しい夢を見ているらしい。
http://rocketnews24.com/2012/04/15/202326/
【夢じゃなくて現実になるアプリがほしい】
■ネズミの意思決定力、人間と同程度? 米研究
~3月15日 AFP通信~ネズミが賢いことはよく知られた事実だが米国の研究チームは13日、情報を取捨選択して最適な判断を下す力において、ネズミは人間に劣らないとする研究結果を発表した。米コールドスプリングハーバー研究所のチームは、餌をやりながら様々な種類の音や映像の刺激をネズミに与える実験を行い、そうした情報をネズミがどのように取捨選択し、餌をもらえる時のパターンを見つけ出すかを分析した。そして人間に対して行った同様の実験と結果を比較したところ、ネズミも人間も、統計上の「最適曲線」に従って意思決定していた。つまり、できる限り最適な道を選択するということだ。
http://www.afpbb.com/article/life-culture/health/2865386/8645840
【わたしの意思決定力、ネズミと同程度。・・・と聞こえてならない】
■泌尿器科は内科?市民約半数が勘違い
~3.20 産経ニュース~日本泌尿器科学会が行ったアンケートで、市民の約半数が「泌尿器科は内科」と誤解していることが分かった。泌尿器科の主要部分は外科治療とされる。「泌尿器科は外科(主に手術を行う)と、内科(主に薬物治療を行う)のどちらに属すると思うか」という設問に、44・5%が「内科」と回答。「外科」は9・3%だった。ただ、高齢になるほど外科と回答する率が高まった。また、「泌尿器科で扱うと思う臓器・部位」を選ぶ設問では、「膀胱」「前立腺」「尿道」「男性性器」などは90%以上が認識していたが、「腎臓」は44・8%と低かった。一方で、約20%が泌尿器科の領域外である「卵巣」「子宮」と回答。市民の泌尿器科に対する理解度は低いようだ。
【部位が部位だけに勘違いも多い。腎臓移植・人工透析も当科ですよ】
■衝撃の真事実!…猫はコタツで丸くならない(〃_ 〃)ゞ
~2012年01月19日秒刊SUNDAY~猫はコタツで丸くならない!こちらの写真はTwitterで話題になったコタツの中の猫を激写した様子。そう言えば猫がコタツの中でどのように過ごしているかはあまり知られていない。試しにGoogleで猫・コタツと調べてみると、沢山の猫とコタツの写真がでてくるが、これといって本当に丸くなっている猫の写真は見当たらない。昔に比べ、今のネコは経済が豊かになったことで横柄になり、コタツを借り物ではなく我が物顔で占拠する為、悠々自適にスペースを使うタイプの猫が多いのかもしれない。昔の猫は今に比べ食料も不足し、猫も飼い主に遠慮するあまり、コタツのスペースさえも利用するには申し訳なく思い、わざわざ丸くなってスペースを開けたと考えられやしないだろうか。(ライター:たまちゃん)
http://www.yukawanet.com/archives/4080339.html
【今のご時世、存在感がもっとも薄いのは亭主なり】
■カキの「貝話(かいわ)」を聞けば、何言ってるかワカル!
香川大学瀬戸内圏研究センターでは、通称「貝リンガル」と呼ばれるセンサーと磁石を使った装置を使い、海水の変化に反応するカキの開閉運動を監視している。センター長は「貝リンガルを使えば『酸素が少なくて苦しいよ!』といった貝の『悲鳴』を聞くことができる」と語る。これまでのところ、カキたちは健康的に会話しているという。
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/science-technology/2844320/8169294
■「バカは風邪ひかない」は本当か!?
「バカは風邪ひかないというのは、じつはあながち無根拠な表現ではないんですよ」そう語るのは池袋スカイクリニックの須田隆興先生だ。「ストレスは確実に免疫機能を低下させます。仕事が多忙な時期にかぎって風邪をひきがちなのは、心身にストレスが蓄積しているためでもあります。“バカ=ストレスを感じない”と解釈するのはいささか乱暴かもしれませんが、少なくともあまり物事に頓着しないタイプの人が、ストレスを蓄積しにくいのは事実でしょう。つまり、風邪をひきにくい傾向は、医学的にあり得ると思います」
http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/wxr_detail/?id=20110613-00020357-r25
■美しい!ゴミが人間に・・・。【画像あり】
シャドーアートの極み。ゴミが生きている人になった。
http://twitpic.com/6os8z2
■世界でもっとも正確な時計
米国立標準技術研究所が所有するNIST-F1という時計。その正確さは1000万年間で1秒もずれないレベル。そこまで正確さが必要かッ!オレの腹時計はですね~、、、常時狂ってる。
http://www.gizmodo.jp/2011/09/10001.html